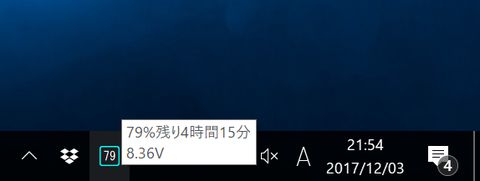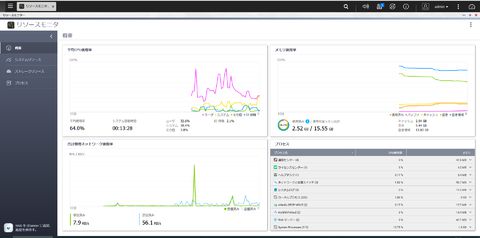最近,こんな記事を見つけた.スマートフォンのバッテリーにまつわる9つの「嘘と真実」
嘘と真実という内容の割には間違いやピントのずれた解説が多くてびっくりした.順番に追っていくと
1.表示が100パーセントでも、まだ充電の余地がある
【真実】
ディスプレイに表示されるパーセンテージより、もう少しだけ充電できる余裕が携帯電話には存在する。だが、それを使ってしまうと全体的なバッテリーの寿命を劇的に縮めてしまうことになる。この問題の要点は、生産工程における繊細なトレードオフだ。
確かに,リチウムイオン単体だけなら満充電以上に充電することができる.これは製造者がバッテリが爆発しないための余裕と,バッテリ寿命を確保するための余裕があるからだ.でもスマートフォンにおいて100%以上充電されることがあるとしたらそれは不良品だ.当然,充電保護回路が組み込まれており,どんなに充電ケーブルを刺しっぱなしにしても100%以上充電することはできない.
2.Wi-FiやBluetooth接続をオンにすると寿命が減る
当たり前の内容すぎてどうにもコメントできない...(苦笑)ただ,この章の解説で以下のような内容が出てくる.
電車に乗っているとき、携帯電話の動きが“重く”なったと気づいたことはあるだろうか。それはおそらくデヴァイスがネットワークに接続するために、エネルギーを使い過ぎているのだ。「例えば鉄道会社が提供しているWi-Fiのように安定したネットワークにつなげられるなら、そこにつないだほうがいいでしょうね」
Wifiやbluetoothと言っているのに何故か携帯回線の話にすり替わっている.意味が分からない.しかも鉄道会社が提供しているWi-Fiは大概多くの人が接続しようとしており,常に混雑している.さらに移動することで線路沿いのAPと干渉を起こしまくるので不安定で電力の消耗が激しくなる.なぜ推奨されているかわからない.
3.純正ではない充電器は悪影響を及ぼす
全くその通りだが,理由として以下のように書かれている.
もし必要以上の電流が供給されているとすれば、たくさんのリチウムイオンをはぎ取っていることになり、先に説明したような損傷が発生してしまう。
スマートフォンの仕組み上,電池に必要以上の電流が供給されることはない.供給されるならそれは不良品である.逆に必要な量よりも供給電力が少ない場合は注意が必要である.本体の電力使用量と充電器の電力供給量が近い場合,本体の瞬間的な電力消費量の変化に合わせてバッテリは充電と放電を急速に繰り返すようになる.すると,バッテリの電極に金属リチウムが析出しやすくなりバッテリが劣化する.結論は正解だが,解説が真逆だ.
4.パソコンにつないで充電すると悪影響を及ぼす【嘘】
前述の理由から,PCの電力供給量が少なく,充電しながら操作する場合は注意が必要である.もちろん充電速度がゆっくりであればその分バッテリへの負荷は小さくなるので一概に間違いとは言えないが.
6.温まっていないと十分に機能しない
【(たいていの場合は)嘘】
実のところ、その反対は真実である。「気温が低い状態でバッテリーを使用することや、バッテリーを冷たいままにしておくことは、寿命の面では非常にいいことです」というのが、グリフィスの言い分だ。
気温が高すぎるのは当然だが,低すぎても金属リチウムが析出しやすくなるため,バッテリには良くない.ハイブリッドカーでは電池を保護するために低温ではHV駆動がOFFになったり,バッテリを温めるためのヒーターが内蔵されていたりするほどだ.
【(あなたが考える理由とは違うが)真実】
これは先の神話とよく似たものだと言える。一晩中ずっと充電し続けて容量を100パーセントに保つのはいいことではないが、それは扱える以上の充電を押し込んでいるからではない。100パーセントまで充電すると充電器からは切り離されるが、少しでも消費したら継ぎ足すようになるからだ。
通常,継ぎ足し充電が起こらないように制御されているためこの解説はおかしい.当然100%をキープするとバッテリに負荷がかかるが,意味合いが変わってくる.
これだけ間違いがあると本当にバッテリの専門家なのかあやしい.こんな記事が巷にあふれている限り,バッテリに対する都市伝説はなくなるはずもない.